
遺品整理はいつから始めるべき?目安となる6つのタイミングを紹介
故人の残した品々を整理する作業である「遺品整理」。いつから始めればよいか、分からないところもあるのではないでしょうか?結論から言うと、遺品整理を始める時期に明確なルールはありません。いつから始めてもよいのです。
ただし個々の状況によっては、遺品整理が遅れるとリスクを負ってしまう場合もあります。そこで本記事では、遺品整理を行う目安となるタイミングを6種類紹介します。最後までお読みいただけると、自身の状況に合わせて遺品整理を始めるタイミングを適切に選べるようになります。
なお本記事では「遺品整理がどのような作業なのか」については解説しておりません。遺品整理について知りたい場合には、以下の記事をご覧ください。
「遺品整理とは?行うべき時期や業者選びのポイント・費用相場を解説」の記事はこちら
目次
- 1-1.気持ちが落ち着いてから
- 1-2.葬儀直後
- 1-3.死亡後の手続きを終えてから
- 1-4.四十九日法要の後
- 1-5.相続放棄の期限が到来する前
- 1-6.相続税の申告前
- 2-1.空き巣や火災、倒壊のリスクが高まる
- 2-2.特定空家に指定される場合がある
- 2-3.遺産相続や相続税の納付に支障が出る
3. 自力で遺品整理が難しければ専門業者へ依頼する方法を検討する
4.まとめ
1.遺品整理はいつから行う?目安となる6つのタイミング

本章では、遺品整理を行うのに適した時期を6種類紹介します。
1-1.気持ちが落ち着いてから
一般的に遺品整理は、気持ちが落ち着いてから取り組めばよいとされています。遺品整理には「いつまでに行わなければならない」という明確なルールがないためです。
無理に遺品整理に取り掛かっても、感情に影響されて作業が進まないことがあります。一方、気持ちに区切りがついた後ならば、残された品々と冷静に向きあえるため、スムーズに遺品整理を進めやすいものです。
一方、事情によっては気持ちに整理が付かなくとも、遺品整理を進めなければならない場合もあります。次からは遺品整理を行う目安となる具体的なタイミングと、どのような事情を抱えている人がその時期に取り組むべきなのかも紹介します。
1-2.葬儀直後
葬儀直後は精神的に辛い時期であり、遺品整理に取り組むのは大変な期間でしょう。しかし、親族が集まる機会のため、相続や形見分けに関する話し合いを進めるには適しています。特に遠方に住む親族が多い場合には、葬儀直後を逃すと話し合いが難しくなるケースもしばしばです。
また故人が施設に入所していた場合、早急に整理を進めなければならないこともあります。たとえば1週間以内に退去しなければならないならば、葬儀後すぐに遺品整理を進めなければなりません。
葬儀直後の遺品整理が推奨されるケース
- 施設の退去期限が迫っている場合
- 親族が遠方に住んでいる場合
- 孤独死に伴い住居の修繕が必要な場合
1-3.死亡後の手続きを終えてから
葬儀後は死亡届の提出や保険証の返納、年金の受給停止など、さまざまな手続きを期日までに行う必要があります。これらの手続きが一段落した後に、遺品整理に取り掛かるケースが増えます。
たとえば故人が賃貸物件に住んでいた場合、退去が遅れると家賃が余計にかかるため、早期に遺品整理が必要です。遺言書や相続財産を早めに確認しておきたい場合にも、死亡手続きの後に遺品整理が行われる傾向にあります。
死亡後の手続きを終えてからの遺品整理が推奨されるケース
- 故人が一人で賃貸物件に住んでいた場合
- 遺言書や相続財産の確認を早めに行いたい場合
1-4.四十九日法要の後
四十九日法要は葬儀後に次いで親族の集まりやすい機会のため、相続や形見分けについて話し合うには適したタイミングです。葬儀後に比べると慌ただしさがなく、落ち着いて親族と遺品整理について話し合えます。
ただし四十九日法要には、必ずしも全員が集まれるわけではありません。集まれる親族のみで話し合いを進めて良いかどうかについて、必ず全員の意向を確認しておく必要があります。関係者の同意なく遺品整理を進めると、親族間のトラブルに発展しやすいため注意が必要です。
四十九日法要後の遺品整理が推奨されるケース
- 親族が遠方に住んでいる場合
- 落ち着いた状況で話し合いをしたい場合
- 形見分けを行いたい場合
1-5.相続放棄の期限が到来する前
故人に借金がある場合には、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄の手続きをしないと、自動的に相続を承認したとみなされ、財産だけでなく借金まで引き継ぐことになるためです。
相続放棄の手続きは、亡くなってからおよそ3か月以内に行わなければなりません。この期間中に遺品整理を進めることで、故人の財産や負債を正確に把握し、相続放棄をするかどうかの正しい判断ができるようになります。
まずは借金の有無だけでも早めに把握しておきましょう。もし相続放棄の必要がある場合には、手続きの期限である3か月を意識して、遺品整理のスケジュールを立てることが大切です。
相続放棄の期限が到来する前までに遺品整理に取り組むべきケース
- あらかじめ故人に借金があることをつかんでいる場合
- 故人の死後に借金が判明した場合
1-6.相続税の申告前
相続税の納付は、故人の死亡を知った日から10ヶ月以内に行わなければなりません。期限を過ぎると、延滞税や加算税の支払いが生じる可能性があります。
相続税の申告・納付の際には、不動産や預貯金、株式、貴金属などの財産を全て含めて正しく評価し、申告書を作成する必要があります。遺品整理を通じて財産の全体像を把握することが、申告書の作成に不可欠です。
ただ相続税は誰もが払う税金ではありません。相続税の基礎控除額を超えた場合に納税の義務が生じます。相続税の基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。この金額を超えて相続すべき財産がある場合に限り、相続税の申告時期を意識して計画的に遺品整理に取り組む必要があります。
相続税の申告期限が到来する前までに遺品整理に取り組むべきケース
- 相続すべき遺産の額が基礎控除額を超えていると予測される場合
- 故人の財産が複雑で、早めに把握が必要な場合
2.遺品整理が遅れることで生じる3つのデメリット

遺品整理を始める時期に明確なルールはありません。しかし、状況によっては早めに取り組まなければ不都合が生じる場合もあります。
そこで本章では「遺品整理の開始が遅れることで考えられるデメリット」を3種類紹介します。
2-1.空き巣や火災、倒壊のリスクが高まる
故人の持ち家が空き家として放置される場合、さまざまなリスクに晒されてしまうものです。
- 無人であることが周囲に筒抜けになり、空き巣被害に遭いやすくなる
- 電気ケーブルや古い家電から自然発火し、火災につながる恐れがある
- 老朽化が進行して、倒壊の危険性が高まる
特に火災や倒壊は近隣住民や通行人にまで被害が及ぶ可能性があるため、看過できないリスクです。これらのリスクを避けるためには、早めに遺品整理を進めるとともに、定期的に住宅のメンテナンスを行うことが重要です。
2-2.特定空家に指定される場合がある
故人の家を空き家として放置しておくと「特定空家」に指定される場合があります。特定空家とは倒壊や衛生問題を引き起こし、周囲の環境に悪影響を与えると判断された空き家のことです。
特定空家に指定されると、まずは自治体から指導や助言を受け、改善の提案が行われます。それでも改善が見られない場合には勧告や命令が下され、固定資産税が最大6倍まで増額されたり過料が課されたりします。
思わぬ経済的な負担を避けるためにも、空き家を放置せず定期的にメンテナンスすることが重要です。もし今後、住む予定のない空き家は、売却や解体などの選択を検討することが望ましいかもしれません。これには遺品整理を完了させておくことが必要です。
なお特定空家に関する情報は、以下のサイトで詳しく確認できます。
住宅:空き家等対策の推進に関する特別措置法関連情報 - 国土交通省
2-3.遺産相続や相続税の納付に支障が出る
遺品整理を進めておかなければ遺産分割協議を進められないため、遺産相続に支障が出る場合があります。遺産分割協議とは「故人の遺産をどのように分けるか相続人同士が話し合うこと」を指し、相続手続きを行ううえで不可欠なプロセスです。
遺品整理を進めていないと、誰にどの財産をどれだけ分けるか決められず遺産相続が滞ってしまいます。つまり遺品整理が遺産相続を円滑に行うための起点となるわけです。
また遺品整理によって財産の概算額を把握しなければ、相続税の申告や納付ができません。相続税の納付期限は「死亡を知った日から10か月以内」と定められており、これを過ぎると無申告加算税や延滞税などが生じます。
遺品整理の遅れにより遺産相続や相続税の納付に支障をきたす可能性がある点は、必ず押さえておくべきです。
3.自力で遺品整理が難しければ専門業者へ依頼する方法を検討する
本記事を読み、自身がいつから遺品整理を始めるとよいか見えてきたかもしれません。しかし、遺品整理には、大きな時間と労力を要します。大型の家具や家電、思い出の品々、スマホのデータなど整理すべき対象が多岐に渡るためです。
故人の残した品々が多かったり人手が足りなかったりすると、自力での遺品整理が余計に難しくなることがあります。このようなときに検討していただきたいのが「遺品整理業者」に依頼する方法です。
遺品整理業者に依頼すれば、遺品の仕分けや不用品の処分、清掃までを全て任せられ、あなたにかかる負担を最小限に抑えられます。しかし業者を頼むとなると、費用がどれくらいかかるのか気になるところではないでしょうか?
以下の記事では、遺品整理の費用相場について詳しく解説しています。
「遺品整理とは?行うべき時期や業者選びのポイント・費用相場を解説」の記事はこちら
ぜひこの記事を参考にして、業者に頼むべきかどうかを検討してみてくださいね。
遺品整理のパートナー「M's」では無料見積もりを承っております。
間取りやお部屋の画像などをお送りいただけますと、お見積もりがスムーズです。
対象エリア:千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、関東近郊
4.まとめ
本記事では、遺品整理に取り組むべき時期について詳しく解説しました。本来、遺品整理に取り組むべき時期に明確なルールはありません。気持ちに整理がつき心が落ち着いた時点で行えばよいのです。ただし状況によっては、以下のように目安を決めて遺品整理に取り組んだ方がよい場合もあります。
| 時期 | 遺品整理が推奨されるケース |
| 葬儀直後 |
|
| 死亡後の手続きを終えてから(死亡日から14日後) |
|
| 四十九日法要の後 |
|
| 相続放棄の期限(相続開始を知った日から3ヶ月)が到来する前 |
|
| 相続税の申告前(死亡日から10ヶ月) |
|
状況によって遺品整理に取り組んだほうがよいタイミングは異なります。上記の事例以外にも、故人の持ち家が空き家になる場合は放置しておくと、火災や倒壊など様々なリスクが考えられます。早めに、遺品整理を進めて売却や解体などを検討したいところです。
特に持ち家の場合には物量が多い傾向にあるため、自力での遺品整理が難しくなる場合があります。遺品整理に十分な人手が確保できない場合には、途方に暮れてしまうかもしれません。この場合には、遺品整理業者を利用して自身の負担を減らせないか検討してみることをおすすめします。
「遺品整理を早く行わなきゃ。でも何から手をつけよう……」
そんなときは迷わず「遺品整理専門M’s」へご相談下さい。



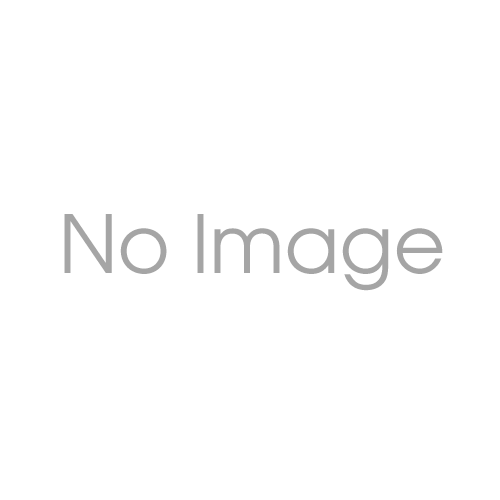.jpg)
