
生前整理の進め方でよくある5つの悩みと解決策を徹底解説
「生前整理」とは人生の終盤を見据えて、身の回りの整理を行う取り組みです。しかし、生前整理を進めようとすると「どこから始めればいいのかわからない」「不用品をどう処分すればいいのか」など、さまざまな悩みに直面することがあります。 本記事では生前整理でよくある5つの悩みを取り上げつつ、具体的な解決策を提案します。この記事を参考にして、生前整理をスムーズに進めましょう。 生前整理のお悩みは「M’s」にご相談ください
\不用品回収から空き家の清掃までお任せの「M’S」/
目次
3.物を捨てられない
- 4-1.方法①自治体に依頼して回収してもらう
- 4-2.方法②自治体指定の処理施設へ持ち込む
- 4-3.方法③テレビや冷蔵庫は家電量販店や自治体指定の業者に回収してもらう
- 4-4.方法④ 知人や他人に譲る
- 4-5.方法⑤リサイクルショップへ売る
- 4-6.方法⑥ オンラインフリーマーケットを活用する
- 4-7.方法⑦ 不用品回収業者を利用する
生前整理でよくある5つの悩みと解決策を紹介
生前整理ではやるべきことが多く、どこから手をつければよいのか迷うことは珍しくありません。この悩みに対して、具体的な解決策を紹介します。
1.何から手をつければいいのかわからない
生前整理ではやるべきことが多く、どこから手をつければよいのか迷うことは珍しくありません。この悩みに対して、具体的な解決策を紹介します。
解決策① 整理しやすい場所から始める
家の中で整理しやすい場所を見つけて着手する方法はおすすめです。たとえば玄関や脱衣所は物が少ないため、短時間で片付けを済ませられます。また冷蔵庫や台所にある賞味期限切れの食品・調味料は、捨てるものの基準が明確で取り組みやすい箇所です。このような取り組みやすい場から整理することで、小さな達成感を得られ、次の作業への意欲も高まります。
解決策② 不要な銀行口座やクレジットカードを解約する
使っていない銀行口座やクレジットカードの整理も、はじめに取り組む作業としておすすめです。仮に家族がクレジットカードや銀行口座を把握し、解約手続きを行うためには多くの時間を費やすことになります。そのため本人が生前整理しておくと、家族の負担を大きく減らせるわけです。 重要ながらもスキマ時間を利用して取り組みやすい活動のため、生前整理の第一歩に適しています。
解決策③ 絶対に見られたくないものと残したいものを優先的に処理
絶対に見られたくないものや、必ず家族に引き継ぎたいものの整理は、生前整理の中でも優先すべき作業です。 たとえば日記やSNSアカウントなど、他人に見られたくないものは早めに処分することで、自分の尊厳を守れます。 一方、家族に引き継ぎたい衣類やアクセサリー、写真などは、誰に渡すのかをエンディングノートにリスト化しておくと、遺族にとって助けになります。
2.最後まで終わらせられるか不安
生前整理を進める中で「終わりが見えない」という不安を抱く方は多いものです。このような不安を軽減するには、無理をせず、自分に合ったペースで進める工夫が大切です。
解決策① 完璧を目指さなくてよいと理解する
生前整理は、すべてを完璧に終わらせる必要はありません。家族が困らない程度に整理できていれば十分です。 生前整理を全くしない人も多いなか、途中まででも整理を進められている自分を認めてあげましょう。完璧さを求めるのではなく、自分ができる範囲で少しずつ整理を進めていけばよいのです。
解決策② 無理のないスケジュールで取り組む
一度にすべてを片付けようとするのではなく、現実的なスケジュールを立てることが効果的です。たとえば、「今週はデスク周り」「来週はクローゼット」など作業を細分化し、1つずつ取り組みましょう。小さな目標を達成するたびに前に進んでいる実感が得られ、不安も軽減されます。
3.物を捨てられない
生前整理を進める中で、物を捨てられずに悩む人は少なくありません。しかし、物を手放さなければ整理が進まないのも事実です。そこで、効率的に物を減らすための具体的な方法を紹介します。
解決策① 残すものと処分するものに基準を設ける
「1年以上使わなかったものは処分する」といった具体的なルールを決めると、整理がスムーズに進み、後悔する可能性も少なくできます。四季を通じて使わなかったものは、今後も使う可能性が低いと判断できるためです。もちろん「すべてルールどおりに処分しなければならない」と決める必要はありません。アルバムや家族写真など、感情的な価値がある物はルールに縛られず、残しておく判断をしてもよいのです。
解決策② 思い出の品は写真に撮ってデータ化する
子供の作品や記念品など感情的な理由で捨てづらい物はスマホで写真を撮り、データ化する方法がおすすめです。写真としてデータに残しておけば、捨ててしまった後もいつでも見返せます。
4.不用品の処分方法がわからない
生前整理では不用品をどのように処分すればよいか分からないと悩む場合が多いもの。特に大型の家具や家電は日常的に捨てる機会が少なく、どう対応すれば良いか困りがちです。ここでは、不用品の処分方法を具体的に解説します。
方法①自治体に依頼して回収してもらう
自治体の粗大ゴミ回収サービスは、大型の不用品を手軽に回収してもらえる方法です。 まず自治体に回収を申し入れ、日程と回収場所を確認します。その後、コンビニやスーパーで「粗大ゴミ処理券」を購入して処分する物に貼り付け、指定された日・場所で回収してもらう流れです。 比較的安価な費用で不用品を回収できる方法ではありますが、回収日まで数週間〜1ヶ月ほどかかる場合があります。また、指定された場所までの運搬は自力で行わなければなりません。
方法②自治体指定の処理施設へ持ち込む
自治体が指定する処理施設に持ち込む方法もあります。 自分の都合に合わせて持ち込めるため利便性が高く、処理費用が安価な処理方法です。しかし、運搬のために車両を用意しなければなりません。自家用車でも構いませんが、タンスやソファなど特に大きな家具を運ぶ際には、軽トラックの手配が必要になるでしょう。
方法③テレビや冷蔵庫は家電量販店や自治体指定の業者に回収してもらう
テレビ・冷蔵庫・洗濯機・乾燥機については家電リサイクル法により、粗大ごみとしては捨てられません。購入した家電量販店か自治体指定の業者に引き渡す必要があります。このとき、リサイクル料金と収集運搬料金の支払いが必要です。 リサイクル料金:3,000〜5,000円程度 収集運搬料金:2,000~3,000円程度 以下のページでは、テレビや冷蔵庫などのリサイクル料金を確認できます。 再商品化等料金一覧(家電リサイクル料金) | RKC 一般財団法人家電製品協会 家電リサイクル券センター
方法④ 知人や他人に譲る
不用品のうち、まだ使えるものを知人や家族に譲ることで、次の人に役立ててもらえます。物を減らせるうえ、周囲の人にも喜んでもらえる方法です。
方法⑤リサイクルショップへ売る
値段がつく可能性のあるものはリサイクルショップを活用しましょう。出張買取サービスを依頼すれば自宅まで査定に来てもらえます。運搬の手間を省けるため、多忙な方や車を持っていない場合におすすめです。
方法⑥ オンラインフリーマーケットを活用する
「メルカリ」や「Yahoo!オークション」など、オンラインフリーマーケットを使って不用品を処分する方法もあります。出品や発送の手間が生じる分、リサイクルショップより高額で売れる可能性が高いため、時間がある場合にはおすすめです。
方法⑦ 不用品回収業者を利用する
不用品回収業者を利用すれば、分別のことを考える必要もなく大量の物品を一度に処分できます。しかし、物が多いほど処分費用は高額です。不用品回収業者の費用相場を以下にまとめます。 不用品回収業者の費用の相場 不用品回収業者の依頼費用は、主にトラックの台数で決まります。
|
トラックの大きさ |
費用相場 |
|
2tトラック / 1台 |
50,000円〜80,000円 |
|
4tトラック / 1台 |
80,000円〜100,000円 |
データ出典元:不用品回収ルート「不用品回収で2t・4tトラックはどれくらい積めるの?積み放題について解説」 2tトラックならば1〜3人暮らしの荷物、4tトラックがあれば一般家庭の荷物全てを載せ切れる容量です。
5.モノの整理以外にやることは?
生前整理に取り組むうえで物を整理する以外にも家族の負担を減らせる活動はあります。具体的には、財産目録とエンディングノートの作成がおすすめです。
財産目録
財産目録は自身の資産を明確にし、相続手続きの負担を軽減するための書類です。預貯金、不動産、保険、株式、借金など、所有する資産と負債をリスト化します。それぞれの保管場所や評価額、受取人の希望を記載しておくと、相続人が対応する際に迷いやトラブルを防げるのがメリットです。
財産目録には特定の書式はありませんが、オンラインで入手できるテンプレートを活用すると、簡単に作成できます。裁判所が提供する「相続財産目録」の書式も参考にするとよいでしょう。
書式は以下のリンクからダウンロードできます。
裁判所|相続財産目録
なお財産目録には法的拘束力はありません。相続人間の協議や遺言書の作成を補助する資料として位置づけられる点にご注意ください。
エンディングノート
エンディングノートは、自身の意向や家族へ伝えるべき情報をまとめておける便利なツールです。遺品リスト、形見分けや葬儀の希望、SNS・アプリのパスワードなどを書き留めておくと、家族の大きな助けになります。
書店で購入できるエンディングノートには、作成の解説書が付いており、スムーズに作成できる点が強みです。一方、自治体や公共機関で無料配布されているエンディングノートならば、コストを抑えて簡単に作成に取り組めます。
エンディングノートを無料配布している自治体一覧
エンディングノートを活用することで、家族が本人の意思に基づき迷うことなく行動できるようになります。今のうちに大切な情報をまとめておきましょう。
困ったら生前整理専門業者への依頼を検討してみましょう

生前整理を進めるうえで、自力では対応が難しい場合や、作業の手間を減らしたい場合には、生前整理専門業者に依頼する方法もあります。
| 間取り | 人数 | 作業料金 |
| 1R・1K | 1〜2名 | 3万円〜8万円程度 |
| 1DK | 2〜3名 | 5万円〜12万円程度 |
| 1LDK | 2〜4名 | 7万円〜20万円程度 |
| 2DK | 2〜5名 | 9万円〜25万円程度 |
| 2LDK | 3〜6名 | 12万円〜30万円程度 |
| 3DK | 3〜7名 | 15万円〜40万円程度 |
| 3LDK | 4〜8名 | 17万円〜50万円程度 |
| 4LDK以上 | 4〜10名 | 22万円〜60万円程度 |
仕分けや不要品の処分、簡易清掃など、生前整理の全行程を代行してもらえるため、時間や労力を大幅に削減できるだけでなく、心理的な負担も軽減されます。また仕分けに困る品物について、専門的な観点からアドバイスを受けられる点も魅力です。 一方、専門的なサービスのため、費用は高額になりがちです。以下に間取り別の大まかな相場を紹介します。
仕分けや不要品の処分、簡易清掃など、生前整理の全行程を代行してもらえるため、時間や労力を大幅に削減できるだけでなく、心理的な負担も軽減されます。また仕分けに困る品物について、専門的な観点からアドバイスを受けられる点も魅力です。 一方、専門的なサービスのため、費用は高額になりがちです。以下に間取り別の大まかな相場を紹介します。 データ引用:遺品整理の専門家による遺品整理ブログ「生前整理を業者に依頼した時の費用相場はどのくらい?」 このように間取りによって相場は決まっておりますが、業者の種類や物量によっても金額は異なります。 そこで、複数の業者から相見積もりを取り、費用を比較することが重要です。料金の比較に加え、対応可能な作業範囲やスタッフの信頼性、口コミや評判も確認しましょう。契約前に作業内容や追加料金が発生する条件などを確認しておくと、トラブルを防げます。 自力での取り組みが難しい場合には、専門業者を利用することでスムーズに生前整理を進められるため、利用を検討してみましょう。
まとめ
本記事で紹介した、空き家を放置したときに起こりうるリスクには以下の4種類があります。
- どこから始めるべきか
- 最後まで終わるか不安
- 物が捨てられない
- 物の処分方法がわからない
- 物の整理以外に何に取り組めばよいのか
本記事ではこれらの悩みに対する解決策を紹介しました。大切なポイントとして生前整理においては完璧を目指す必要はありません。優先度の高い作業から進めていくことで整理の流れが見え、モチベーションを維持しやすくなります。
とはいえ生前整理は時間と労力を要する作業です。自力での整理に行き詰まるときには、専門業者に相談する方法もおすすめできます。生前整理の専門業者「M’s」なら仕分けから処分、清掃までを一括でサポート。経験豊富なスタッフが丁寧に対応し、ご自身やご家族の負担を大きく軽減できます。
\空き家整理、どのように進めるか迷ったら「M’S」へご相談を/



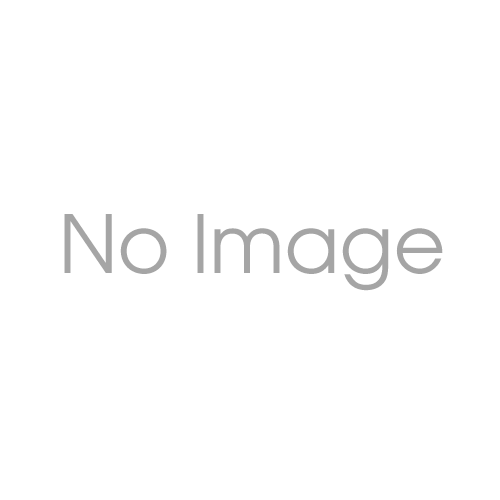.jpg)
